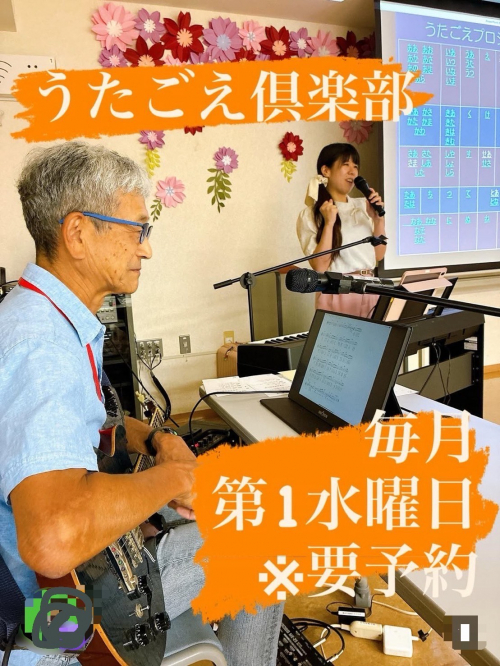2025.09.07
- 活動報告
【横浜市霧が丘地域ケアプラザ】防災訓練に参加してきました!
2025年9月7日(日)霧が丘連合自治会防災訓練に参加しました。
今回の防災訓練は、外国籍の方も多数参加され、200名程の方が参加されていました。
5つのグループに分かれ、はまっこトイレの設置、煙体験、スタンドパイプ放水、拠点テントの設置、休憩をグループごとに体験しました。
はまっこトイレの設置では、組み立て式の便座と外枠をグループのメンバーで声をかけあい協力しながら作りました。一度経験のある方でも手順を慎重に考えながら作っていました。「実際に災害があったときにも今のように慌てないように作業しなきゃね。」と実際に災害が起きた時を想定した緊張感で行っていました。


小さな部品が入った箱にはわかりやすく大きくテプラが貼ってありました。

このカーテンは、地域の方が作ってくださったそう。周りから見えないように配慮されています。


煙体験では、訓練用の煙を炊いたプレハブに入っていきます。進行を邪魔する壁も作られていて、戸惑う方もおおかったようで、実際に災害が起きた時と同様の緊張感がありました。外に出てくるとみなさんほっとした様子。「全く前が見えなかった。」「何もおさえるところがなくて不安になった。」などお話が伺えました。
では、実際に煙でまえが見えなくなったときはどのようにまえに進めばよいのでしょうか?消防隊員からの回答は、どちらでも構わないので、右か左と決めて、壁を触った状態で前に進んでいく方法。同じ側の壁を伝って歩いていくと必ず出入り口に回ってこれる。それが遠回りかもしれないが、途中で左右を変えないように同じ方向を伝って歩き進むことが大切とのことでした。


スタンドパイプ放水では、地域の防火水槽の場所の確認と、ふたの開け方、パイプのつなげ方のを訓練しました。質問もあり、一つ一つ答えていただきながら訓練を行いました。




パイプがつながったら、放水訓練へ!

大量の水が一気に出てくるので、大人一人の力では支えきれません。そのため、必ず後ろにも一人補助についてもらうこと、準備ができたら、「放水はじめ!」と大きな声で指示を出し、水が出てきたら手元の水の出口をひねって放水の幅を調整する。火が消えたら、「放水止め!」と大きな声で指示をだす。
大人の男性二人で行っていても、水が出るときには手元がぶれる様子があったので、かなりの力が加わるのだと感じました。
拠点テントは体育館の中で行いました。ワイヤーが使われている簡易テントの広げ方と畳み方。段ボールベッドの設置の仕方や、寝転んだり座ったりして強度も体験しました。
最後に、希望者の方の消火訓練を行いました。訓練用の消火器ではなく本物の消火器を使った訓練です。グラウンドで行いましたが、本物の火は外でも恐怖を感じるほどの大きさで、消火器を向けるのもとても緊張したと思います。実際の消火器を使うことでどれだけの勢いがあるのか、煙が立つのかなどの経験ができました。

休憩時間には、外国籍の方との交流もあり、地域のつながりが広がる瞬間が見受けられました。実際に災害が起きた時に、協力し合える顔見知りの方が少しでも多くなるように、日ごろからのつながりを大切にしたいと思った訓練でした。
横浜市霧が丘地域ケアプラザH.T