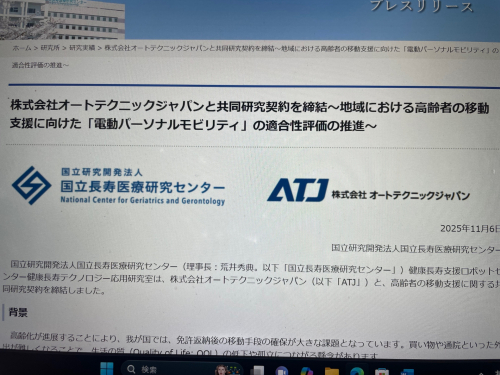2025.11.12
- ニュース
大規模調査で「在宅医療の利用に数十倍の地域格差がある」ことを確認
横浜市立大学大学院データサイエンス研究科ヘルスデータサイエンス専攻及び頴田病院総合診療科らの研究グループは、全国335の二次医療圏(都道府県が定める医療計画の地域単位で、一般的な入院医療が圏域内で完結することを目指す地域)を対象とした大規模調査から、在宅医療の利用に数十倍から200倍以上の地域格差が存在すること、また日本の医療における「へき地度」を表す尺度が高い地域ほど在宅医療の利用が少ない傾向にあることを明らかにした、と発表しました。実は、「この研究は人口密度だけでなく、医療機関までの距離、豪雪地帯、離島などの地理的要因を統合的に評価することの重要性を示している」とも述べています。ご存じの通り、「へき地」では高齢化率が高く、医療アクセスが限られています。国土の61%が山地で約400の有人離島を持つ日本では、在宅医療が地域包括ケアシステムの中核として期待されているわけです。ただ、「訪問診療、往診、看取りなど在宅医療の多様な機能ごとの格差や、人口密度以外の地理的要因の影響は十分に検証されていなかった」とのこと。そこで、本研究では、「全国335の二次医療圏における在宅医療利用の標準化レセプト出現比を算出し、訪問診療で82倍、往診で210倍という大きな地域格差を確認した」と言います。今回の研究の結果を受けて、「在宅医療は医療者が患者宅を訪問するため、豪雪や離島などの地理的条件の影響を受けやすく、これらの要因を考慮した政策立案が求められること」また、「地理的制約のある地域では、医師や看護師の増員だけでなく、タスクシフティングやナースプラクティショナーの配置など多職種連携の強化が重要であること」を示しています。本研究グループは、「今後は、個人レベルのレセプトデータを用いて市町村や郵便番号レベルでのより詳細な分析を行い、季節変動の検証や、疾病負担の違いを考慮した格差評価を実施する予定である」と結んでいます。
在宅医療の利用に数十倍の地域格差 -Rurality Index for Japanを活用した全国調査で明らかに- | YCU Research Portal
画像はプレスリリースから引用させていただきました。
SM