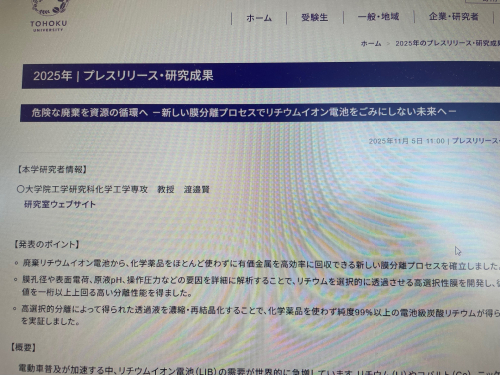2025.11.07
- ニュース
アルツハイマー病とパーキンソン病の両方に共通する脳の仕組みとは?
アルツハイマー病とパーキンソン病の脳内の信号伝達を妨げる共通のシナプス機構が明らかになり、神経変性症状の共通原因が特定された、と発表したのは沖縄化学技術大学院大学の研究グループです。因みに、シナプスは「様々な機能を制御する神経回路に関与する、脳内コミュニケーションのハブ」なのだそうです。従って、記憶に関わる神経回路のシナプスにタンパク質が蓄積すると記憶が障害され、運動制御に関わる神経回路に蓄積すると運動障害が引き起こされるとか。ところで、脳の情報伝達を支える小胞の働きについて、当プレスリリースは次のように説明しています。神経伝達物質は脳細胞内で精製され、シナプス小胞(小さな膜の袋)の中に貯蔵され輸送されます。この小胞は、移動してシナプス間隙に神経伝達物質を放出され、そこで拡散し、近くの細胞にある受容体に到着。その後、小胞がまた回収され、神経伝達物質を再び充電して再利用されるという事です。本研究では、この回収プロセスを阻害し、脳の正常な情報伝達を妨げる分子を特定したそうです。その結果、脳細胞間のシナプス伝達もコミュニケーションも妨げられ、結果としてアルツハイマー病やパーキンソン病が発症するという事です。本研究グループは、今回の研究成果を受けて、三つの治療ターゲット、すなわち疾患関連タンパク質の蓄積の防止、微小管の過剰な生成集合の阻止、そして微小管とダイナミンの結合の阻害という治療ターゲットを特定することで、新たな治療法の開発を目指していきたいと結んでいます。加えて、2024年に報告を行ったマウス実験でのアルツハイマー病症状を改善するペプチドについてですが、このペプチドがパーキンソン病の症状緩和に応用できる可能性がある事についても言及しています。
アルツハイマー病とパーキンソン病に共通する脳の仕組みを発見 | 沖縄科学技術大学院大学(OIST)
SM