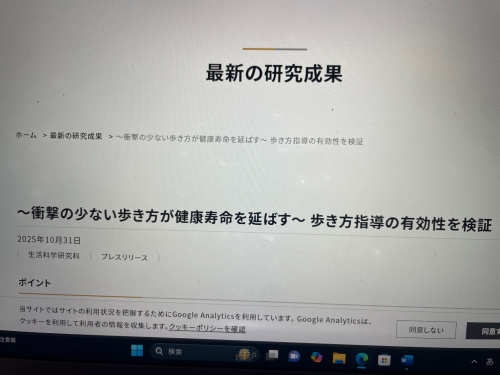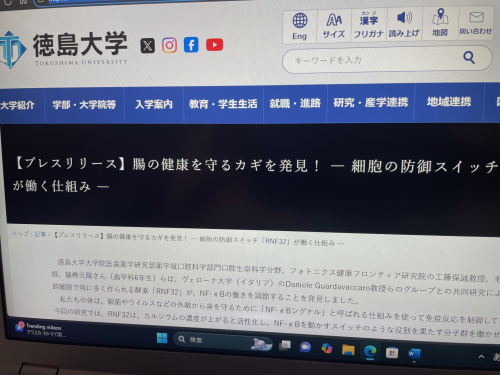2025.11.05
- ニュース
クマが出た!
クマの大量出没がマスコミで報道されています。人身事故も頻繁に起こっています。そして、町に出没するクマに「アーバンベア」という名称がつけられるようになりました。この名称を含めて、本当にクマが人慣れしたのか、クマの個体数は増えたのか、増えたとしたらどのくらいの数なのか、自然観察を通じてその根拠を積み重ねていかなければならないと論じるのは、自然写真家で著述家である永幡嘉之氏です。彼の著書「クマはなぜ人里に出てきたのか」の中で、クマ問題について様々な視点で論じています。興味深いのは、クマが住宅地に出てくる場所には共通点があることです。クマは川に沿って樹林のある場所、河川敷がある場所の付近に集中していること、夜間にえさを求めて下りてきて、夜明けまで餌を食べている間に、町は早朝の活動が始まり、人間も動き出し、クマは森に帰れずパニックになって人家に飛びこんだりしているという共通点があると指摘しています。もう1点、クマの個体数が増加しているという意見ですが、その自然増加率は餌の豊作や凶作によって変動するだろうということです。ともあれ、上述の著書では、「クマの変化は人間の生活の変化に対応していた」と述べています。すなわち、大きく3つの変化がクマの行動にも変化をもたらしたというのです。一つ目は、中山間地域での生活の変化で、人口の減少が主な原因。「無人」となってしまった地域にクマが頻繁に出現するようになったこと。二つ目は、「人間の感覚の変化」。かつては、山の中で暮らしていた人々は、クマの痕跡に気づき、生活圏に出てこないように対策を取っていたこと。それがクマへの抑制策になっていた点です。それから、永幡氏は「狩猟の方法の変化」について次のように言及しています。かつては、クマを人々が囲って狩りを行っていたため、クマも人間の圧力を学習して警戒心が強かったのですが、現在はライフル銃の性能が上がり、数百メートル離れた場所から正確に撃つことができるといいます。つまり、「ここには出てきてはいけない」と場所を確認する場面がなくなりつつあると述べています。ともあれ、クマとの共存はどのように可能なのでしょうか?クマを獲り尽くして絶滅させる?それでは生物の多様性の問題を棚上げすることになります。例えば、捕獲して人里離れた場所に放つ、発信機をつけて行動を把握する、柿などクマを引き寄せる木を伐採する、電気柵の設置やロボットの活用、そして長期的には、どのように森林を残していくのか、その広さや豊かさは、など考えうる課題がたくさんありそうです。
SM