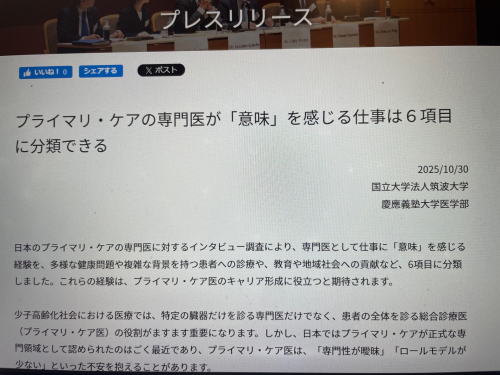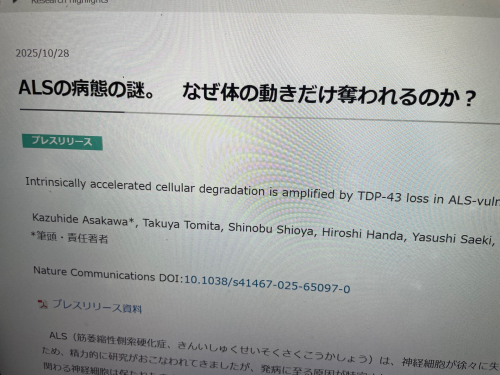2025.11.05
- ニュース
他者に共感する脳の働きとは?
「怖いという気持ちを共感するときの脳の働きを、マウスを使って解明した」と数年前に東京大学定量生命科学研究所らの研究グループが発表しましたが、その研究では相手の怖いという気持ちに共感するときに「自分の恐怖」と「他者の恐怖」の両方の情報を併せ持つ神経細胞が前頭前野という脳の領域に存在することが分かったそうです。具体的には、実験マウスが、電気ショックによって恐怖反応を示す別のマウスを見て、同じように恐怖反応を示したそうです。加えて、マウスがその場でうずくまって震える「すくみ行動」をやめることなく恐怖を感じている別のマウスをじっと観察する行動を続けたといいます。こうした行為を「共感」と呼ぶとすれば、自分と他者の境界が一時的になくなるように感じられる現象であり、互いにコミュニケーションを築く上で重要な役割を果たしているといいます。すなわち、脳内に存在する「ミラーニューロン」という神経細胞が痛みや喜びを分かち合っているのです。ところで、10月31日付東京新聞の記事の中で脳科学者の田中昌司氏は、「脳は相手を自分の仲間とみなすかによって、共鳴の度合いを調整している」と指摘しています。私たちは「互いに映し合う」脳を持っているということのようです。因みに、ミラーニュートンですが、動物が行動すると他者が同じ行動を行うのを観察するときの両方で活動する神経細胞で1990年代にイタリアの科学者らによるサルの研究で発見されたそうです。
「共感」する時の脳のはたらき ――自分と他者の情報を合わせ持つニューロンの発見―― | 東京大学 定量生命科学研究所
画像はプレスリリースから引用させていただきました。
SM