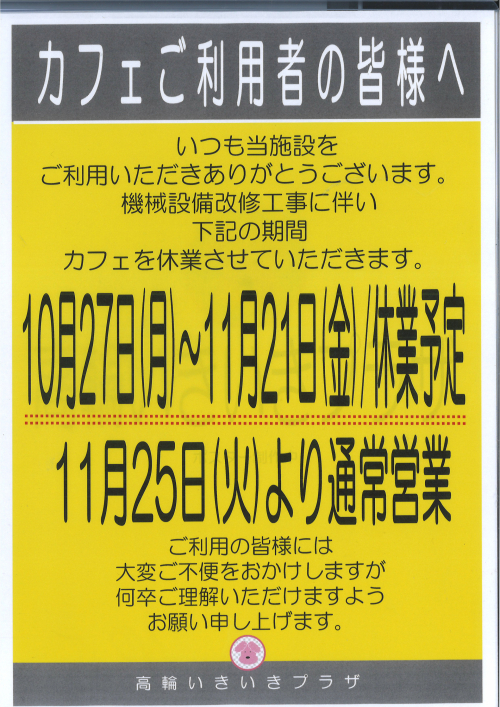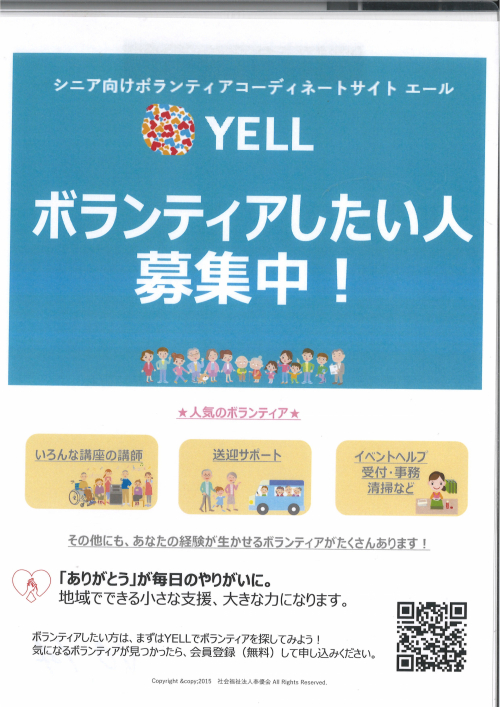2025.10.24
- ニュース
睡眠時無呼吸症候群とは?
睡眠中に呼吸が10秒以上停止する状態のことを睡眠時無呼吸というのだそうです。千葉大学大学院医学研究院呼吸器内科学のHPに教えられました。また、いびきを伴い、1時間あたり5回以上無呼吸や低呼吸が発生し、そのために熟眠できず、日中など起きている時間に異常な眠気を催す状態になることを「睡眠時無呼吸症候群」といいます。当HPによると、「脳、神経、心臓の病気が原因で起こるタイプを中枢型、のどが閉じてしまうことで起こるタイプを閉塞型、両者が混合して起こるタイプを混合型」と呼ぶのだそうです。因みに、夜間に呼吸が苦しくなる夢を何度もみるなどの症状は睡眠時無呼吸症候群が原因ではないかということです。しかし、どうして睡眠時無呼吸症候群は起こるのでしょうか?例えば、閉塞型。肥満などがあると、仰向けになって入眠しても鼻や口から入ってきた空気は滞りなくのどを通過して気管・肺に入っていくのですが、眠るとのどが狭くなり、空気が通りにくくなることがあるため、狭いのどを空気が通過して「いびき」が発生。そして、さらに、そこの部分が完全に閉塞してしまうと、無呼吸になるという訳です。ともあれ、自分がどのタイプなのか(中枢型、閉塞型、混合型のどのタイプか)を診断することが重要だとか。なぜなら、それぞれに応じて治療の必要性などがあるからです。ところで、診断のための検査は二段階で行うとか。まず、簡易検査を行って陽性になれば、本検査へ。気をつけたいのは、日中、眠くなることが必ずしも睡眠時無呼吸と関連していない場合もあるようです。より詳しい検査は、「ポリソムノグラフィー」と呼ばれ、指先の器械だけではなく、心電図や脳波、鼻や口の気流測定、腹部の動きなどを見るセンサーなどを装着して、一晩休んで検査します。つまり、1泊2日の入院が不可欠です。最後に、治療法ですが、CPAP(鼻にマスクをあて、そこから空気を送りだしてのどがふさがらないようにする治療法)やマウスピースを装着してのどがふさがらないようにすること、あるいは横向きで寝ることで気道を確保することなどがあります。そして、外科手術により、小型デバイスシステム「舌下神経電気刺激装置」を完全に体内へ植込み、夜間の呼吸に合わせて、舌下神経という舌の動きをつかさどる神経に電気刺激を与えることで、 舌根(ぜっこん)を持ち上がらせて気道が閉塞しないようにする治療法もあります。ただ、この治療を受けるにはいくつかの条件があり、例えば18歳以上であること、 高度肥満ではないこと(BMI 30未満)、CPAP 療法が継続困難であることなどが挙げられます。ともあれ、お酒を飲んで入眠すると、粘膜の浮腫が生じいびきをかきやすくなりますので、くれぐれもこの症状が疑われる方は入眠する前に飲酒することは控えて下さい。飲酒の中止のみで症状が改善することもあることをお忘れなく。
睡眠時無呼吸症候群 :: 千葉大学大学院医学研究院 呼吸器内科学
SM