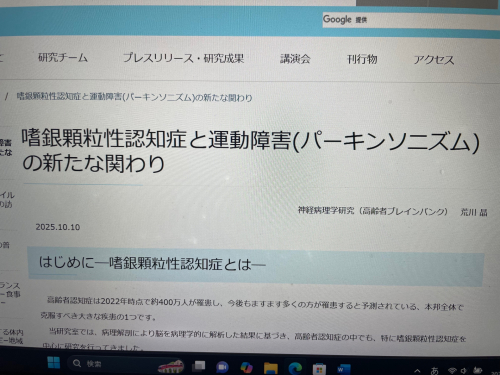2025.10.15
- ニュース
脳が体の声を聞いておいしさを実感
私たちが食べたり飲んだりしておいしいと感じるのは、体内状態に応じて変化するのだそうです。ただ、そのおいしいという価値を脳内でどのように計算しているのか、そのメカニズムの実体は不明だったとか。そこで、大阪大学医学蛋白質研究所および国立精神神経医療研究センターらの研究グループは、「脳内のドーパミン神経が体内の水分と塩分のバランスに応じて、水分または塩分を摂取した際のそれぞれの価値を計算していることを世界で初めて明らかにした」と発表しました。具体的には、マウスの実験で「マウスが感じる水と塩のおいしさと脳内ドーパミン反応のパターンにおいて喉が渇いている状態と塩分不足の状態で逆転することが分かった」と述べています。すなわち、渇水状態において水を摂取すると高いドーパミン活動が起こりますが、逆に塩分を摂取するとドーパミンを抑制したそうです。一方、塩分不足の状態で塩水を摂取するとドーパミンは増加。ただの水の摂取はドーパミンを抑制、という結果になったといいます。要は、ドーパミン反応が体内の水分と塩分のバランス次第で真逆になるという訳です。本研究グループは、今回の研究成果は「体内の状態に応じた食事のおいしさの客観的な評価法への応用に役立つことが期待される」と結んでいます。因みに、ドーパミンは中枢神経系の存在する神経伝達物質で快感や幸福感、意欲や運動調節などに関する脳内ホルモンです。余談ですが、パーキンソン病はドーパミンの不足によって起こりやすくなると言われています。
画像はプレスリリースから引用させていただきました。
SM