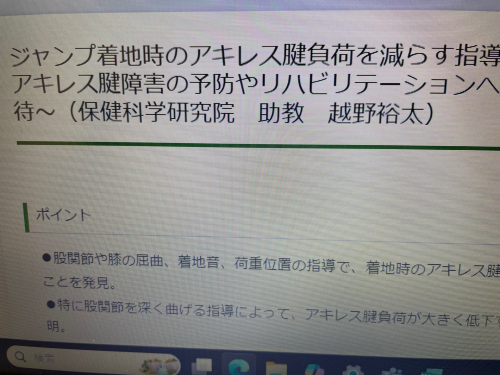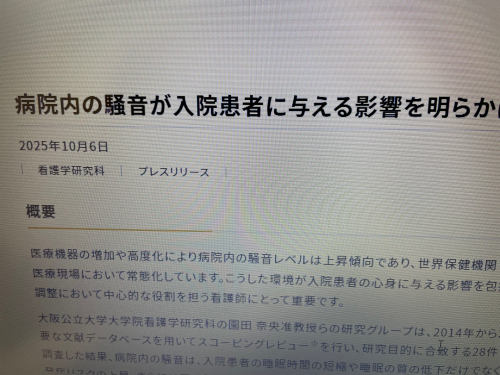2025.10.08
- ニュース
下肢動脈疾患の新たな治療法
日本血管外科学会のHPによると、「足の動脈が狭くなったり詰まったりして血液の流れが悪くなり、足にさまざまな症状を引き起こす病気」は、現在、「末梢動脈疾患」という名称に統一されているそうです。その原因ですが、多くは動脈硬化によって、腹部大動脈から下肢動脈が詰まるためだとか。注意したいのは、動脈硬化を原因とする狭心症や心筋梗塞、脳梗塞などを合併することが多いため、末梢動脈疾患のある人は全身の動脈硬化症についても目を光らせておく必要があると述べています。ところで、脚の血管に動脈硬化があり、それが重症化すると足先が壊死し、脚の切断に至るケースもあるようです。10月7日付東京新聞の記事によると、下肢動脈疾患の初期には歩くとふくらはぎが痛み、少し休むと改善するという症状がみられるようですが、進むと安静時にも痛みが続くといいます。さて、治療法ですが、実は、今まで膝より下の血管治療のための「器具の実用化」は難しいとされていました。しかし、同記事によると、東海大学医学部や慶応大学理工学部らの研究チームが血流を改善するメッシュ状の金属製の筒「ステント」を開発し、その治験が行なわれています。実は、膝より下の動脈は直径5ミリ以下と細いため、治療しても、再狭窄が起きやすいのだとか。そこで本研究グループは、「異物として認識されると血流を妨げる組織が増殖して再狭窄が起きるので、そうならない素材でステントを開発。ダイヤモンド膜で覆った新型ステントの開発に成功した」そうです。ナノメートル単位に薄くした素材と、徐々に溶け出す薬剤の効果で異物反応や炎症を抑えられ増殖を防ぐことも確認できたと述べています。因みに、国内には直ちに治療が必要な下肢動脈疾患の人がおよそ18万人いるということです。
医学部が日本発・世界初となる「膝下血管病変向け薬剤溶出型ステントシステム」の医師主導治験に関する記者説明会を開催しました | ニュース | 医学部 | 東海大学 - Tokai University
新技術利用ステント注目 細く血流弱い膝下の動脈硬化に対応 ダイヤモンド膜で覆い異物反応抑える:東京新聞デジタル
SM
SM