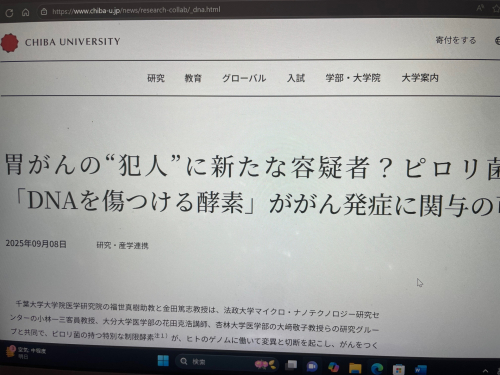2025.09.12
- ニュース
氷のタイムカプセル
火星と聞けば、私たちに馴染みのあるタコのような火星人を連想しますが、最初に火星人の存在が意識されたのは18世紀前半だったそうです。19世紀後半には火星全体の表面に線状模様があることを発見し、火星には「運河」があるのではないかと言われました。その後、20世紀後半に多くの火星探知機が火星を観測し、また地上からも高性能の望遠鏡による観測が可能になり、線状模様に見えたものは運河どころか火星表面にはほとんど水が存在しないことが判明、火星人がいないことも分かりました。ただ、私たちにとって火星は、フィクションの火星人も含めて、身近な存在であることに変わりはありません。さて、前置きが長くなりましたが、岡山大学学術研究院先鋭研究領域(惑星物質研究所)らの研究グループは、「NASAの探査機による高解像度画像を用いて、中緯度の750以上のクレーターを調査した結果、氷によって形成された地形やクレーター年代、さらに気候モデルを組み合わせることで、過去約6 億年の氷の蓄積と分布の変化を明らかにした」と発表しました。実は、火星は約6億4千万年前には氷が厚く広がっていたのですが、その後減少し、最後の氷の蓄積(約9800万 年前)では限られた分布になったそうです。これは、火星が湿潤な時代から乾燥寒冷な時代へ移行したことを示しているといいます。本研究グループは、「過去には現在よりも氷の蓄積量が多く、現在は大きく減少していることを明らかにし、火星の氷安定性と気候進化の理解を進展させるとともに、将来の有人探査に向けた水資源の利用にもつながる重要な知見である」と結んでいます。
火星の気候変動の足跡:中緯度クレーターに記録された氷のタイムカプセル - 国立大学法人 岡山大学
画像はプレスリリースから引用させていただきました。
SM