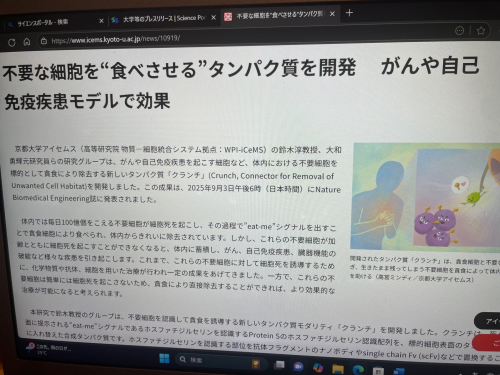2025.09.10
- ニュース
認知症の「空白期間」
認知症と判断される前に、二つの「空白期間」が存在するそうです。一つは、「違和感を覚えてから診断を受けるまでの期間」、もう一つは「診断を受けてから介護保険サービスを利用するまでの期間」です。この概念は、この期間に外部からの支援が届かず、本人が孤立・孤独に苦しむリスクが大きいために、注目に値すると述べるのは、東京都健康長寿医療センター研究所の研究チームです。実際、本研究では2点確認したそうです。一つは「空白の期間が、時代と共に短くなっているかを比較すること」。もう一つは、空白の期間ⅠおよびⅡが、長くなる事例の特徴を明らかにすること。そこで分かったことは、調査分析の結果、空白の期間Ⅰは8.3か月から13.6か月に変化したが統計学的な有意差はなったそうです。また、空白の期間Ⅱは、27.1か月から5.9か月に統計学的にも有意に短くなっていたそうです。次に、空白の期間が長い事例の特徴ですが、空白の期間Ⅰ(気づき~診断)の平均値は13.5か月。空白の期間Ⅱ(診断~介護)の平均値は16.9か月だったとか。本研究グループは、「ここで注意していただきたいのは、当事者が空白の期間を問題にしたのは、『空白』すなわち絶望的な状況にあることを指しており、早く診断を得たい、早く介護保険サービスを受けたいといった『長さ』ではないということです。とはいえ、絶望や孤独を調べることは難しく、定量的にも捉えにくいため、私たちはまずは『長さ』という非常に単純な要素に注目して調査しました」とコメントしています。そして、本研究は、空白の期間の長さは短くなっているということを示したものだと述べています。加えて、長い間、診断や介護に出会わない事例の特徴が明らかになったとも。さらに、地域包括支援センターや医療機関は、このような特徴を持つ事例に出会った場合には、診断になかなか至らない、介護開始が遅くなる、といった可能性があることは認識したうえで接することは有意義であるとも述べています。最後に、本研究グループは、「今後は空白の期間の絶望や孤立が本当に解消されていたのか、それを解消するにはどうすればよいのかという研究を行っていきたい」と結んでいます。
<プレスリリース>認知症のいわゆる「空白の期間」の研究|研究成果|地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所
画像はプレスリリースから引用させていただきました。
SM