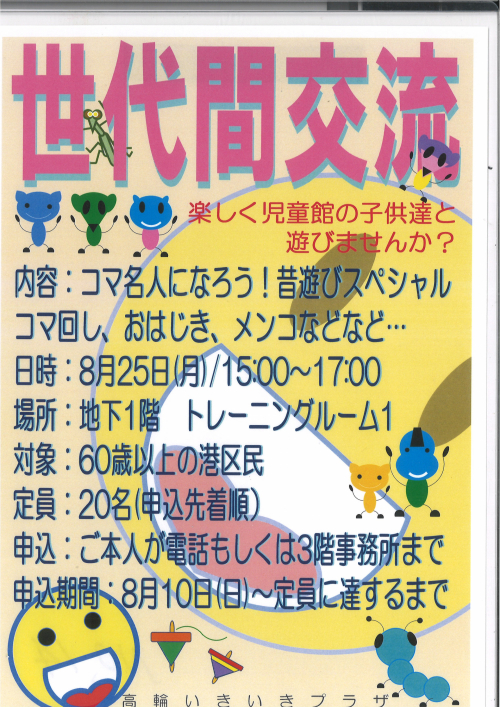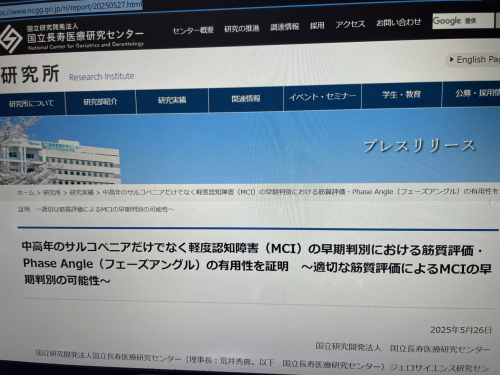2025.08.20
- ニュース
食道の動きを数式で見える化
嚥下障害は⾷道の動きの異常が原因で 、誤嚥性肺炎などのさまざまな病気の元になるといわれています。近年、このような⾷道の動きの計測⼿法が発達して、⾷道特有の不思議な挙動が数多く明らかになってきましたが、これらがどのように起こるのかまだよく理解されていなかったそうです。そこで、九州大学大学院医学研究院系統解剖学分野らの研究グループは、「⾼精度の蠕動運動の計測⼿法と数理モデルとを組み合わせて、⾷道に特有の蠕動運動のメカニズムを解明する枠組みを開発することに成功した」と発表しました。具体的には、⾷道の動きをシンプルな数式で再現する新しい数理モデルを開発。このモデルは、「脳からの指令」→「腸の中の神経ネットワーク」→「筋⾁の動き」という流れを再現したもので、特に、下部⾷道括約筋と呼ばれる部分では“オン・オフ”の切り替えスイッチのような仕組みも取り込まれたそうです。実際に、正常な⾷道がどのように⾷物を運ぶかを再現できたほか、さまざまな病的な⾷道の動きも、パラメーターを調整することで再現できたと述べています。本研究グループは、今回の数理モデルは、ヒトの⾷道蠕動運動の仕組みを理論的に解明するための第⼀歩であり、今後さまざまな応⽤が期待できるといいます。まず、異常な⾷道運動がどのように起こるのか、その原因をパラメーターの組み合わせから推測できるため、疾患の発症メカニズムの理解に役立つ可能性があります。さらに、将来的には、より複雑な「ジャックハンマー⾷道」などのねじれた形状を持つ状態を再現するために、モデルを⼆次元化することも計画しているそうです。神経の種類ごとに別々の動きを取り込むことで、薬の効果をシミュレーションするような応⽤も期待できます。そして、本研究の成果は、「⾷道の病気の原因解明や、新しい治療法の開発にもつながる可能性がある」と結んでいます。
食道の動き、“数式”でわかる!? | 研究成果 | 九州大学(KYUSHU UNIVERSITY)
画像はプレスリリースから引用させて頂きました。
SM