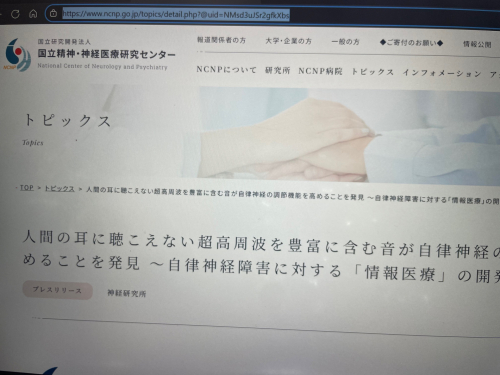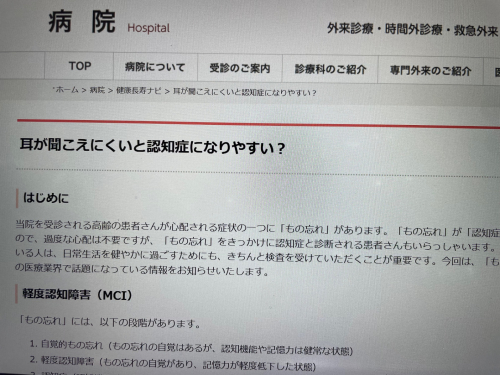2025.08.20
- ニュース
認知症とは?
国立長寿医療研究センターの「認知症って何?アルツハイマー病と違うの?」と題する記事によると、認知機能とは「記憶、見当識(時間、場所)、判断(問題が起こった時に解決できるか?)、遂行機能などで構成されるそうです。ただ、その認知機能は「加齢」によって低下し、日本人を対象とした調査によると55歳から64歳あたりでMMSEと呼ばれる認知機能の点数が低下し始めることがわかっているとか。一方、認知症とは「記憶や見当識といった認知機能が日常生活に支障をきたす程に異常になった場合に該当します(例えば、人と約束したこと自体をすっかり忘れてしまう、なじみのスーパーに買い物に行ったが帰り道がわからなくなるなど)」。そして、認知症の半分以上はアルツハイマー病であり、あとの半分近くは血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭葉型認知症などに該当するということです。さて、アルツハイマー病ですが、アミロイドβ、あるいはタウと呼ばれる蛋白質が凝集、蓄積して発症します。その診断ですが、当センターによると、まず神経心理検査でどのような認知機能がどれくらい落ちているかを調べるそうです。次に、脳MRI検査で脳のどの部位がどれくらい萎縮しているかを調べます。因みに、加齢による海馬の萎縮は年に1から2%程度ですが、典型的なアルツハイマー病では4から5%にまで上昇するとか。そこで、アルツハイマー病の疑いがある方はアミロイドPETや脳脊髄液検査を行います。レビー小体型認知症については、MIBG心筋シンチで心臓の交感神経の障害(末梢神経にαシヌクレインが蓄積することによる)が検出されるといいます。もしアルツハイマー病とレビー小体型認知症の合併がある場合は、「複数の異常蛋白質が溜まっている(つまり複数の疾患病変が存在する)ことがしばしば観察される」と述べています。治療薬についてですが、レカネマブとドナネマブの臨床試験では、脳内に溜まったアミロイドβを減らすことに加えて、認知機能や自立して生活を送る能力の低下を30%程遅らせる効果(症状の進行をおよそ7.5カ月遅らせる効果)が認められたということです。問題は、抗体医薬を投与した患者においても、認知機能は低下を続けてしまうという点を指摘しています。当センターのHPによると、アミロイドβに対する抗体医薬を用いた治療が有効なのは、「抗アミロイド抗体医薬の投与をできるだけ早く開始すること」だとか。なぜなら、脳にアミロイドβが溜まってから、20-30年後に発症するため、この長い潜伏期間の間に、アミロイドβは脳内で炎症を起こして、神経細胞へのダメージやタウタンパク質の蓄積など、脳に修復不可能な病変を引き起こすからです。レカネマブやドナネマブを早期アルツハイマー病の患者に投与することで、認知機能の低下を遅らせることはできますが、完全にとめることはできないとも述べています。つまり、レカネマブやドナネマブですべてが解決するわけではないのです。そこで、私たちが日頃できる予防は次の通りです。①食事(栄養バランスのとれた食事)②運動(散歩やラジオ体操)③良質な睡眠(深い眠りは脳内の老廃物を除去してくれる)④人との交流(会話して脳への刺激を増やす)。ともあれ、不安のある方は早めにご相談を!気になる段階だからこそ、予防対策になることをお忘れなく!
認知症って何?アルツハイマー病と違うの? | 国立長寿医療研究センター
画像はプレスリリースから引用させていただきました。
SM