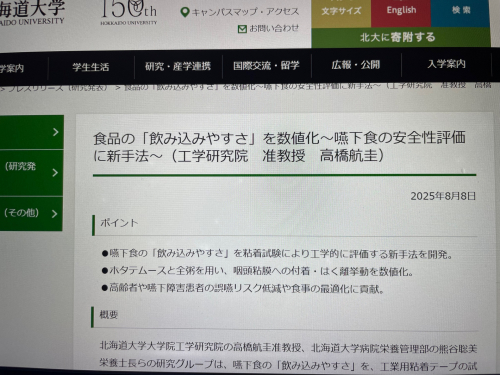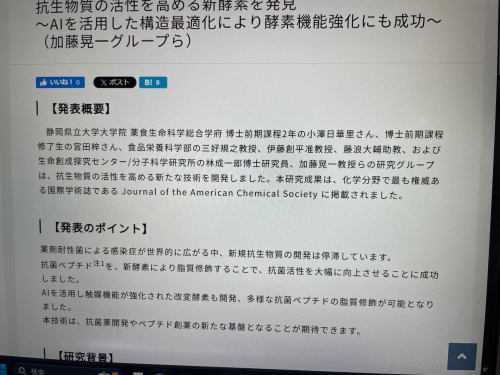2025.08.13
- ニュース
魚の発する“光”から鮮度判定できる技術とは
「魚から発せられる“光”から鮮度を判定する技術を開発した」と発表したのは、広島大学医学部4回生(研究当時)宮崎夏帆さんと同学原爆放射線医科学研究所らの研究チームです。「サーモン、タイ、ブリの3種類に共通して、鮮度の低下(酸化)が進むと、ある光のパターンが強くなることを発見した」と述べています。生物が本来持っている蛍光(自家蛍光)を詳細に解析することにより、鮮魚の鮮度を非破壊的かつ定量的に評価できる可能性を調査し、少なくとも、トラウトサーモン、マダイ、ブリの3魚種に共通する蛍光成分を同定したそうです。実は、魚の鮮度を見極めるのは、これまでは、熟練した職人の“目利き”によって判断されてきましたが、日本国内ではその担い手不足が深刻な社会課題となっているとか。実際、今日では魚の内部状態の変化を非破壊で検出できる手法として「自家蛍光スペクトル」に注目が集まっているといいます。当プレスリリースによると、「自家蛍光」とは、外部から色素などを追加することなく、物質や細胞自体が光を発する性質のことで、その光の波長を「自家蛍光スペクトル」と呼ぶのだそうです。ただ、こういった光を用いた計測は、光の照射条件や個体差、魚種間の成分構成の違いに左右されやすく、一般化された鮮度指標としての運用には課題が残っていたようです。そこで、本研究チームは、「トラウトサーモン・マダイ・ブリの切り身を同一条件下で冷蔵保存し、4種類の波長(275、365、405、455 nm)で発生した自己蛍光スペクトルを時間経過とともに測定した」と述べています。これは、魚種間で共通する酸化指標の探索と、自己蛍光スペクトルの実用的活用に向けた一歩だとか。本研究グループは、今後は、より多くの魚種および保存条件での検証を進め、普遍的な自己蛍光解析モデルの構築を目指します、と結んでいます。
【研究成果】魚の鮮度を“光で読む” ―酸化の進行を光で見抜く技術を医学部生が開発― | 広島大学
画像はプレスリリースから引用させていただきました。
SM