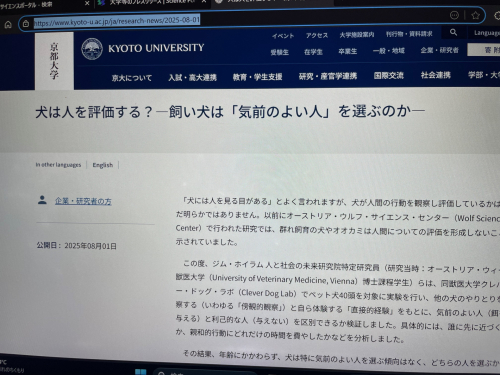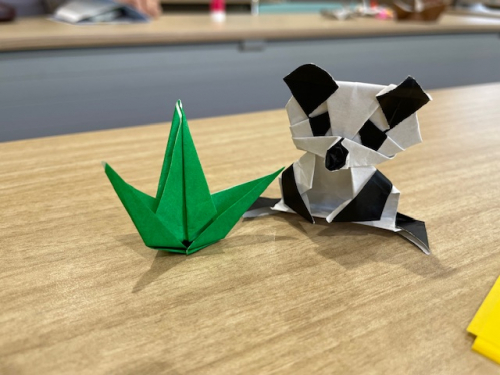2025.08.06
- ニュース
アルツハイマー病とレビー小体型認知症の複合病態と神経細胞死の進行
「アルツハイマー病とレビー小体型認知症の複合病態で神経細胞死が進行する」と発表したのは、早稲田大学理工学術院らの研究グループです。この複合した病態を、モデルマウスを用いて検証したといいます。アルツハイマー病もレビー小体型認知症も、異なるタンパク質が神経細胞内に凝集して蓄積し、機能障害を起こして、最終的に細胞死に至りますが、蓄積するタンパク質であるタウタンパク質とα-シヌクレイン(タンパク質の一種)を同時に神経細胞に過剰発現させ、マウス個体で検証した研究はこれまでなかったそうです。因みに、レビー小体とは、タンパク質が固まってできる小さな丸い構造物で、このレビー小体こそが病気のもとなのです。ただ、なぜ集まってかたまりになるかは分かっていません。本題に戻りますが、本研究では、「それぞれの疾患のモデルマウスを掛け合わせダブルトランスジェニックを作り、単独のモデルマウスと比較した」そうです。その結果、タウ病変の悪化と神経細部死の進行などの障害の進行が認められたといいます。本研究グループは、「今回の研究により、ヒト疾患においても、両者の蓄積は病態を進行させる可能性がある」と述べています。ところで、アルツハイマー病とレビー小体型認知症はともに認知症の原因疾患ですが、日本ではレビー小体型認知症はアルツハイマー病についで2番目に患者数が多いと言われています。アルツハイマー病では神経細胞内にリン酸化されたタウタンパク質が、レビー小体型認知症ではリン酸化されたα-シヌクレインが凝集し蓄積することで、機能障害や細胞死が起こり、認知機能の障害に至ることはすでによく知られています。さらに言えば、「シヌクレインの蓄積が中脳のドーパミン産生神経細胞に主に起こり、細胞死が引き起こされるのがパーキンソン病」です。本研究グループは、「今回新たな知見を得ることが出来ましたが、これは今後の研究に向けた一歩目であり、今後さらに研究を発展させていきたいと考えています」と結んでいます。
アルツハイマー病とレビー小体型認知症の複合病態で神経細胞死が進行する – 早稲田大学 研究活動
画像はプレスリリースから居引用させて頂きました。
SM