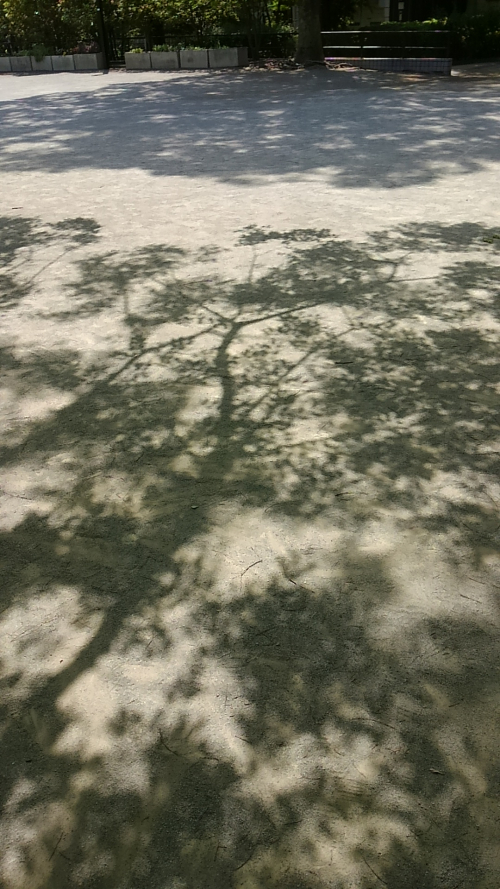2025.06.25
- ニュース
骨粗しょう症による骨折予防は?
「骨粗しょう症による骨折の5年生存率はがんよりも低い」という事実をご存じですか?6月17日付東京新聞の記事が愛知医科大学の中村幸男特任教授の上述のコメントを紹介していました。つまり、骨粗しょう症は軽視できない重要なテーマなのです。近年、骨粗しょう症の治療薬が次々に発見されています。また、骨の老化のメカニズムも解明されつつあります。今までは骨粗しょう症は主に加齢やホルモンバランスの変化、栄養不足などが原因とされていましたが、愛媛大学大学院医学系研究科の研究グループは、「骨芽細胞におけるMen1遺伝子の欠損が、AMPK/mTORC1を介してSASP因子を分泌する細胞老化を誘導し、骨の老化を起こすことを明らかにした」と発表しました。つまり、「細胞老化に伴う骨粗しょう症」というわけです。また、東北大学大学院歯学研究科顎口腔矯正学分野の研究グループは、「塩分摂取によって高血圧になるマウスにおいて、骨を吸収する破骨細胞が増加し骨粗鬆症を引き起こすことを発見した」と述べています。このように「骨粗しょう症」の研究は様々な角度から行われているのです。さて、そうした中、私たちにとって骨密度を低下させない食事療法は不可欠です。骨を構成する主成分はカルシウムですが、栄養素の中でも体内への吸収率は極めて低いとか。そこで、ポイントとなるのがビタミンD。たとえば、サケ、うなぎ、干しシイタケ、きくらげなど。加えて、ビタミンKの存在も忘れてはなりません。納豆、ホウレンソウ、小松菜、ブロッコリー、ひじきなどに多く含まれています。従って、このカルシウム・ビタミンD・ビタミンKの三位一体で骨密度を維持することが需要なのです。さらに、日光浴。最後に、骨は、負荷がかかるほど骨をつくる細胞が活発になり、強くなる性質があると言われています。 散歩や軽いジョギング、階段の上り下りなど、日常生活のなかでできるだけ運動量を増やしていくこともお忘れなく。
細胞老化が引き起こす骨粗しょう症-骨の老化メカニズムを解明- | プレスリリース | 愛媛大学
画像がプレスリリースから引用させていただきました。
SM
塩分による高血圧が骨粗鬆症を誘発するメカニズムを解... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-